こんにちは!
現在の就職活動では安定した職場で働くことを求める学生が多いです。
そのため企業の将来性を気にして企業選びをする際に「業界天気図」など活気のある業界なのか調べる学生も多いと思います。
儲かっている業界に就職すれば、同じような仕事をしてももらえる給料は変わってきますし、企業が倒産する可能生も低いでしょうから当然のことだといえます。
しかし、活気のある、儲かっている業界が必ずしも将来も安定している就職先とは限らないのです。
今回はその理由をいくつか紹介したいと思います。
将来なんて誰にも分からない
未来のことは誰にも分かりません。
世の中には将来のことを予想する仕事があり、彼らはいくつかの根拠を集めて将来を予想します。しかし、一人ひとり意見が異なり、予想したことが当たる人もいれば外れる人もいます。
就職活動にも関係する代表的な例として、銀行業界があります。
銀行業界は、バブル景気の頃(1980年代~1990年ごろ)まで「銀行に就職すれば将来の安定は約束されたもの同然」といった考えられていました。
しかし、現在ではどうでしょうか?
バブル景気崩壊後、「失われた20年」と言われるなかで銀行業界はなかには破綻してしまったり、生き残るため再編を重ねました。そして、最近ではFintech(フィンテック)の台頭によって銀行自体の存在が問われています。
また、最近ニュースでは、これからは「電気自動車の時代だ」、「AI(人工知能)の時代だ」などと言われています。確かにそうなるかもしれません。
しかし、それは必ずしも決まったことではないのです。
つまり、未来のことはそのときになってみないと分からないものですし、他人の予想したものを鵜呑みにすることは良くないことなのです。
業界天気図はあくまで業界の現在の状態を表しているもの
就職関係者やマスコミが毎年出す「業界天気図」や企業の現状はあくまで現在の状態を表すものであるということです。
そもそも、人は調子の良いものを見たときは「今後もさらに良くなるだろう」、悪いもの見たときは「今後、さらに悪くなるんじゃないか」と考える傾向があります。
この傾向がよく現れる例が株式市場です。
株式市場では、株価が上昇するときは「さらに株価はあがるかも」と考える人が多いので株を購入する人が増えます。逆に株価が下落するときは「会社が倒産するのではないか」「さらに値下がりするのではないか」と考える人が多いので株を売る人が増えます。
このような、現在良いものは「さらに良くなる」、悪いものは「さらに悪くなる」傾向は「業界天気図」にも現れます。
つまり、業界の状況が良いからといって今後も良いとは限らないのです。
将来は自分で予想することが大事
では、どうすればいいのでしょうか?
それは「将来を自分で予想する」ことが大切です。
予想が合っている、間違っているかどうかは関係ありません。
自分自身で将来を予想して、予想通りに上手くいった場合と予想に反し上手くいかなかった場合の両方の対処法を考えておくのです。
例えば、就活をして就職した企業・業界で実際に働いてみて将来性がないなと感じた場合で考えて見ましょう。
実際に働いて将来性がないと感じたのならば、リストラや解雇に備えて資格を取得したり、転職活動をおこなったり、副業をはじめることを考えましょう。
しばらくして、自分の予想通りになりそうなら考えたことを実行し、自分の予想に反したなら、そのまま働く選択をすれば良いでしょう。
このようなことを応用して、就職活動において「将来性のない」といわれている業界をあえて選択するというのも一つの選択肢だと思います(あくまで自己責任でお願いします)。
つまり、いちばん大切なことは、「まわりの意見に流されず、自分で考え実行する」ことだと私は思います。


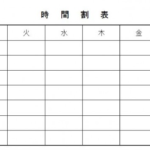

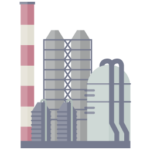



-150x150.png)